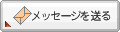2010年10月21日
「東アジアの物流拠点としての沖縄の港湾の現状と課題」ニュース
沖縄を東アジアの物流拠点に
――瑞慶覧長敏・玉城デニー両議員研究会を開始、月1回開催――
瑞慶覧長敏(沖縄4区)・玉城デニー(沖縄3区)の両衆議院議員が主宰して「東アジアの物流拠点としての沖縄の港湾の現状と課題」をテーマにした研究会が設置され、その第1回が10月14日、議員会館で開かれました。
研究会は、グローバル経済の下、東アジアの物流および港湾(空港を含む)の国際化の取組みを分析し、沖縄の地勢的位置を活かした戦略的な港湾・空港政策のあり方を研究し、今後の方向性・具体化の案を作成し、沖縄振興計画の現行に続くポスト振計への「一提言」にしようとの考えです。
民主党沖縄県連の上里直司政調会長(沖縄県議)らが参画し、国土交通省や沖縄県、内閣府沖縄総合事務局の港湾担当者らの協力を得て、毎月1回のペースで開き、来春(2011年3月か4月頃)には調査・研究・討議を「提言」としてとりまとめる予定。
☆港湾戦略で沖縄の
位置づけを鮮明にすべき
さる8月、国土交通省が国際的なハブ(拠点)港を目指して阪神港(大阪、神戸港)と京浜港(東京、川崎、横浜港)の2港湾を「国際コンテナ戦略港湾」に選定し、合わせて、全国の主要な重要港湾(103港)のうち、国直轄の新規事業として予算を配分する「重点港湾」を43カ所に絞り込みました。
「重点港湾」には沖縄県内で「那覇港」と「中城湾港」の2港が入り、このほか「石垣港」「平良港」なども国の直轄港湾整備事業の対象となりました。
「アジア」をにらんだ港湾整備戦略という政府(国土交通省)および民主党国土交通部会の政策展開に大いに期待を寄せていますが、東アジア各国の港湾・空港の国際化の進展ぶりを直視しますと、わが国の
計画・構想には課題が多いようです。
とくに、「アジア」をにらむ港湾戦略というのであれば、那覇港をはじめ沖縄県内の港湾の位置づけをより鮮明にすべきだと考えています。
☆新たな沖縄振興計画の柱に
沖縄の港湾(空港)の東アジアをにらんだ戦略的な整備は、沖縄の経済的・社会的自立を生み出すとともに、わが国のアジア戦略の展開に資するに違いありません。
このような認識に立ち、当面、那覇港の「国際港湾機能」強化の現状を切り口として、東アジア各国の港湾整備の現状の分析を踏まえつつ、「東アジアの物流拠点としての沖縄の港湾(空港を含む)」づくりの「構想」を、急ぎ打ち出す必要があるのではないかと考えています。
「構想」は、現在最終段階となっている現行の沖縄振興計画に代わる新たな沖縄振興計画の「柱」ともなりうると確信しています。「提言」に、乞うご期待!
《メモ》第1回(10月14日)の研究会での報告は次ページに要約していますので、ご参照ください。
《予告》第2回研究会は11月上旬。
*<注意>「万国之津梁(しんりょう)とは、国ぐにの橋渡しになるという意。「津梁」には人びとを導くという意味もある。
<第1回研究会(10/14)の報告>
テーマ:那覇港の国際流通港湾化に
向けて(取組みの経緯と課題)
報告者:内閣府沖縄総合事務局
開発建設部長 浦辺 信一 氏
【要点】
1、昭和63(1988)年の那覇港港湾計画の改訂で、港湾の事業が那覇地先から浦添地先へと大きく展開することになり、那覇港の国際化の整備は、それまでの那覇市単独では対応できないとして、沖縄県や浦添市も含めた広域行政として対応してきた。
2、その後、平成14年(2002年)3月、県・那覇市・浦添市の3者による一部事務組合「那覇港管理組合」が設立され、那覇港の国際流通港湾化に向けた取組みが進んでいる。
3、内閣府沖縄総合事務局としても、那覇港の国際流通港湾化の実現をめざして中村英夫東大名誉教授(運輸政策研究所所長)を委員長(座長)にした学識者検討委員会を設置して審議してもらった。同委員会は議論をとりまとめて、平成14年(2002年)2月に沖縄県知事に対し、「国際トランシップ港湾実現への提言」を報告した。
4、その中で、①那覇港の地理的優位性を活かし、②中国を出入りするコンテナ貨物量の急増が見込まれ、20フィートコンテナ換算(TEU)で百万TEUの取扱いを目標に(H20年代後半には約60万TEUにする)、③韓国の釜山や台湾の高雄など先進港湾と同様のサービス水準の実現をめざすべき―と提言。

(国際コンテナターミナルでの荷役状況)
そのため具体的には「水深13メートルの第2バースの早期完成」「港湾利用のコスト軽減」「港湾の情報化施策」「物流を重視し、観光と連携し、新たな雇用創出可能な自由貿易地域の展開」「官と民、港湾・海事関係者らが参加した『戦略チーム』(物流機能支援体制)の確立」「フィーダー(支線)航路網拡充に向けた戦略的ポートセールス」などの施策を示した。
5、さらに、官民一体となった「沖縄国際物流戦略チーム」が発足し、2008年2月に「沖縄の国際物流戦略に関する提言――万国之津梁を目指して」を取りまとめ、同様な提言をしている。

(9号・10号バースと総合物流支援施設)
6、このような提言をふまえて、国際コンテナターミナルとして第9号バースと第10号バースがそれぞれ供用を開始(1997年8月と2006年1月)し、国際企業(インターナショナル・コンテナターミナル・サービス社ICTSI)をはじめ国内関連企業による「那覇国際コンテナターミナル株式会社」NICTI)が設立され、2006年1月から事業を開始。また、総合物流支援施設(ロジスティックスセンター)の整備も計画されており、外貿コンテナ貨物の荷さばき、一時保管、流通加工、配送機能の物流拠点となる予定である。
7、また国際コンテナターミナル供用を機に、国際コンテナ航路が2航路から6航路に拡充された。それに伴い、外貿コンテナ(実入り)の取扱いは2000年の約5万TEUから2008年の約6万TEUに、2割増えた。
【質疑】意見交換では「重点港湾に指定された那覇・中城湾両港の整備のテンポは?」「整備に向けた用地の確保はどうか」「アジア各国の港湾整備、荷動きの現状を知りたい」「那覇港の国際化の努力はわかるが、取扱量がそう増えていないのはなぜか」「那覇港の利用の企業のメリットは?」などの質問が出た。これに対して「11号バースも整備し、コストダウンなどに取り組む」「利用する企業の声をもって聞く必要がある」との考えが示された。 ◇◇◆◇◇
――瑞慶覧長敏・玉城デニー両議員研究会を開始、月1回開催――
瑞慶覧長敏(沖縄4区)・玉城デニー(沖縄3区)の両衆議院議員が主宰して「東アジアの物流拠点としての沖縄の港湾の現状と課題」をテーマにした研究会が設置され、その第1回が10月14日、議員会館で開かれました。
研究会は、グローバル経済の下、東アジアの物流および港湾(空港を含む)の国際化の取組みを分析し、沖縄の地勢的位置を活かした戦略的な港湾・空港政策のあり方を研究し、今後の方向性・具体化の案を作成し、沖縄振興計画の現行に続くポスト振計への「一提言」にしようとの考えです。
民主党沖縄県連の上里直司政調会長(沖縄県議)らが参画し、国土交通省や沖縄県、内閣府沖縄総合事務局の港湾担当者らの協力を得て、毎月1回のペースで開き、来春(2011年3月か4月頃)には調査・研究・討議を「提言」としてとりまとめる予定。
☆港湾戦略で沖縄の
位置づけを鮮明にすべき
さる8月、国土交通省が国際的なハブ(拠点)港を目指して阪神港(大阪、神戸港)と京浜港(東京、川崎、横浜港)の2港湾を「国際コンテナ戦略港湾」に選定し、合わせて、全国の主要な重要港湾(103港)のうち、国直轄の新規事業として予算を配分する「重点港湾」を43カ所に絞り込みました。
「重点港湾」には沖縄県内で「那覇港」と「中城湾港」の2港が入り、このほか「石垣港」「平良港」なども国の直轄港湾整備事業の対象となりました。
「アジア」をにらんだ港湾整備戦略という政府(国土交通省)および民主党国土交通部会の政策展開に大いに期待を寄せていますが、東アジア各国の港湾・空港の国際化の進展ぶりを直視しますと、わが国の
計画・構想には課題が多いようです。
とくに、「アジア」をにらむ港湾戦略というのであれば、那覇港をはじめ沖縄県内の港湾の位置づけをより鮮明にすべきだと考えています。
☆新たな沖縄振興計画の柱に
沖縄の港湾(空港)の東アジアをにらんだ戦略的な整備は、沖縄の経済的・社会的自立を生み出すとともに、わが国のアジア戦略の展開に資するに違いありません。
このような認識に立ち、当面、那覇港の「国際港湾機能」強化の現状を切り口として、東アジア各国の港湾整備の現状の分析を踏まえつつ、「東アジアの物流拠点としての沖縄の港湾(空港を含む)」づくりの「構想」を、急ぎ打ち出す必要があるのではないかと考えています。
「構想」は、現在最終段階となっている現行の沖縄振興計画に代わる新たな沖縄振興計画の「柱」ともなりうると確信しています。「提言」に、乞うご期待!
《メモ》第1回(10月14日)の研究会での報告は次ページに要約していますので、ご参照ください。
《予告》第2回研究会は11月上旬。
*<注意>「万国之津梁(しんりょう)とは、国ぐにの橋渡しになるという意。「津梁」には人びとを導くという意味もある。
<第1回研究会(10/14)の報告>
テーマ:那覇港の国際流通港湾化に
向けて(取組みの経緯と課題)
報告者:内閣府沖縄総合事務局
開発建設部長 浦辺 信一 氏
【要点】
1、昭和63(1988)年の那覇港港湾計画の改訂で、港湾の事業が那覇地先から浦添地先へと大きく展開することになり、那覇港の国際化の整備は、それまでの那覇市単独では対応できないとして、沖縄県や浦添市も含めた広域行政として対応してきた。
2、その後、平成14年(2002年)3月、県・那覇市・浦添市の3者による一部事務組合「那覇港管理組合」が設立され、那覇港の国際流通港湾化に向けた取組みが進んでいる。
3、内閣府沖縄総合事務局としても、那覇港の国際流通港湾化の実現をめざして中村英夫東大名誉教授(運輸政策研究所所長)を委員長(座長)にした学識者検討委員会を設置して審議してもらった。同委員会は議論をとりまとめて、平成14年(2002年)2月に沖縄県知事に対し、「国際トランシップ港湾実現への提言」を報告した。
4、その中で、①那覇港の地理的優位性を活かし、②中国を出入りするコンテナ貨物量の急増が見込まれ、20フィートコンテナ換算(TEU)で百万TEUの取扱いを目標に(H20年代後半には約60万TEUにする)、③韓国の釜山や台湾の高雄など先進港湾と同様のサービス水準の実現をめざすべき―と提言。

(国際コンテナターミナルでの荷役状況)
そのため具体的には「水深13メートルの第2バースの早期完成」「港湾利用のコスト軽減」「港湾の情報化施策」「物流を重視し、観光と連携し、新たな雇用創出可能な自由貿易地域の展開」「官と民、港湾・海事関係者らが参加した『戦略チーム』(物流機能支援体制)の確立」「フィーダー(支線)航路網拡充に向けた戦略的ポートセールス」などの施策を示した。
5、さらに、官民一体となった「沖縄国際物流戦略チーム」が発足し、2008年2月に「沖縄の国際物流戦略に関する提言――万国之津梁を目指して」を取りまとめ、同様な提言をしている。

(9号・10号バースと総合物流支援施設)
6、このような提言をふまえて、国際コンテナターミナルとして第9号バースと第10号バースがそれぞれ供用を開始(1997年8月と2006年1月)し、国際企業(インターナショナル・コンテナターミナル・サービス社ICTSI)をはじめ国内関連企業による「那覇国際コンテナターミナル株式会社」NICTI)が設立され、2006年1月から事業を開始。また、総合物流支援施設(ロジスティックスセンター)の整備も計画されており、外貿コンテナ貨物の荷さばき、一時保管、流通加工、配送機能の物流拠点となる予定である。
7、また国際コンテナターミナル供用を機に、国際コンテナ航路が2航路から6航路に拡充された。それに伴い、外貿コンテナ(実入り)の取扱いは2000年の約5万TEUから2008年の約6万TEUに、2割増えた。
【質疑】意見交換では「重点港湾に指定された那覇・中城湾両港の整備のテンポは?」「整備に向けた用地の確保はどうか」「アジア各国の港湾整備、荷動きの現状を知りたい」「那覇港の国際化の努力はわかるが、取扱量がそう増えていないのはなぜか」「那覇港の利用の企業のメリットは?」などの質問が出た。これに対して「11号バースも整備し、コストダウンなどに取り組む」「利用する企業の声をもって聞く必要がある」との考えが示された。 ◇◇◆◇◇
Posted by 沖縄4区・瑞慶覧チョービン at 17:01│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。