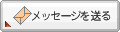2012年01月30日
【港湾政策】民主党港湾議連による東京港視察(2012年1月23日)
民主党にはさまざまな議員連盟がありますが
(興味深いところでは、宝塚歌劇団を応援する「宝塚議連」、
動物愛護政策推進のための「動物愛護議連」、
超党派ですと花粉症対策施策を話し合う「ハクション議連」、
映像文化の発展を応援する「映画議連」などが有名です)、
港湾を選挙区に抱える議員が多く参加する「港湾議連」というものがあります。
衆議院沖縄第四区選出議員である私は、八重山諸島をはじめ離島を多く抱えていますので、選挙区内の港湾の数も、数多の議員の中で上位。
また、沖縄の港湾を東アジアゲートウェイの玄関として発展させ「万国の津梁」を目指すという政策は、私自身のライフワークです。
そのライフワークを推進するために、私とデニーの二人で、月1ベースの勉強会「東アジアの物流拠点としての沖縄の現状と課題」を開催している身でもあります。
したがって、港湾の施策というのは私の活動の中でも大きなウェイトを占めているのですが、今回は港湾議連の主催で、身近でありながら意外と知らない「東京港」の視察に行ってまいりました。
【東京港ホームページ(東京都港湾局)】
http://www.kouwan.metro.tokyo.jp/
さて、私自身も不勉強だったと反省しているのですが、東京港は、今、この瞬間も日進月歩の進化を遂げています。一方で、海も陸も、常に大渋滞。
そんな環境下で、香港・上海・シンガポール・釜山・寧波・ドバイといったアジアの国際港との激烈な競争にさらされているのです。
ここに、「コンテナ取扱量の港湾ランキングの推移(世界)」という参考資料があります。
1991年には178万TEUで世界12位であった東京港。
最新のデータによる取扱量は、約2.4倍の420万TEU。
では、世界ランキングは?
なんと27位に滑り落ちてしまっています。
トップは、上海港の2,907万TEU。
2位は、シンガポール港の2,847万TEU。
3位は、香港港の2,353万TEU。
4位が、深セン港の2,251万TEU。
ここまでが2,000万クラスの取扱量を誇るトップ港です。
すべてが東アジア域に集中しているということも興味深い事実ですが、東京港が取扱量を倍増しているのにもかかわらず、ハブポートとしての存在感を示せなくなっているという事実に、愕然としました。
また、現在、東京・川崎・横浜という近接する三港がそれぞれ経営を異にしていますが、国際競争力の強化のためにも、コスト削減・政策実現のスピードアップという観点からも、三港の一体的な経営が急務といえましょう。
ご参考までに、平成20年のデータになりますが、3港を合算した取扱量は760万TEU。
これはロサンゼルス港の786万TEU に匹敵し、NY港やロングビーチ港を抜いて世界17位までランキングが上昇する値です。
さて、ここからは視察のご報告。議員が上京することの少ない月曜日であるにもかかわらず、20名弱も参加があり、多さに思わず驚きです。
まずは東京ゲートブリッジへ。
中間径間部の橋上に立ちながら東京港を見渡し、しばし説明を受けます。

同行くださった東京都港湾局の担当官によれば、
「世界トップレベル奪還を目指し、日本のハブポートとして北米航路における東アジアの国際ハブポートになる」という将来像を描いているそうです。
そのための重要施策として、「コンテナ物流に関する国際競争力の強化」、
具体的には ①国際基幹航路の維持、②三港の一体的な経営、③港をとりまく交通ネットワークの充実・強化、④船舶大型化への対応、⑤コンテナターミナルの整備・充実、⑥オフドック機能の拡充などを挙げておられました。

東アジアのメインポートとして、大きく変革を遂げて実力を伸ばした韓国・釜山港に対峙できる日本のハブポートを目指すとの力強いご説明に、
「那覇港もうかうかしていられないな」と、
つい地元を思い浮かべてしまいます。

左斜め前方が、羽田空港。羽田側からは海底トンネルでゲートブリッジへ入ります。
しばし、議連でお借りしたミニバスの車窓から東京湾を視察しながら、議員同士で意見交換。選挙区に港湾を抱える議員は、皆さん真剣そのもの。
しかし、バス内で説明があったとおり、ターミナルまでの渋滞に早速巻き込まれてしまいました。東京港は、特に利用者ニーズが高く、ヤード内では常にコンテナで満載状態、周辺道路の青海地区・大井地区の最大渋滞は7Kmにおよび午後4時ごろには通常10分程度の距離で行くべきものが80分もかかってしまう状態になるとのこと。航路の渋滞とともに、大問題です。企業は、こうした物流コストの無駄をもっとも嫌いますので、大商業地・大集積地に近いという東京港のインセンティブが効かなくなってしまいます。

現在、臨港道路南北線事業・臨港道路南北線接続事業が計画されており、これが実現すると現在の混雑箇所のバイパスにもなりますので、輸送力の強化が期待できます。
昼過ぎに、大井埠頭のコンテナターミナルに到着。
埠頭からターミナルを遠景とともに拝見。

前方左の箱状のものが、世界初の立体型コンテナ集積所です。
実は、つい先日の16日~18日、デニーと釜山港・釜山新港を視察に行ってきたばかりです。
その報告は、別の機会にしっかりさせていただきますが、
徹底的に合理化された釜山新港のコンテナターミナルの凄さを身にしみて感じてまいりました。
船舶大型化に対応した水深16メートル、奥行き600メートルの大型バース。
また、1バースあたりガントリークレーンを3~4基配備(通常は2基)、
トランスファークレーンはすべてオートメーション化し、
オペレータールームから遠隔操作するなど、徹底した設備投資ぶりには、驚愕の一言でした。
そして、その設備投資は、国籍を問わない民間資本によるもの。
運営も民間企業による経営です。
大井埠頭コンテナターミナルも懸命にメンテナンスや設備投資を行っていますが、圧倒的な質・量を兼ね備える釜山新港とついつい比較し、しばし無言に。
やはり、港湾政策の充実は急務です。
今日の知見は、釜山港・釜山新港の視察とともに地元に持ち帰り、
那覇港の発展のために活かしてまいりたいと考えています。
万国の津梁を目指し、まだまだ頑張ります!
(興味深いところでは、宝塚歌劇団を応援する「宝塚議連」、
動物愛護政策推進のための「動物愛護議連」、
超党派ですと花粉症対策施策を話し合う「ハクション議連」、
映像文化の発展を応援する「映画議連」などが有名です)、
港湾を選挙区に抱える議員が多く参加する「港湾議連」というものがあります。
衆議院沖縄第四区選出議員である私は、八重山諸島をはじめ離島を多く抱えていますので、選挙区内の港湾の数も、数多の議員の中で上位。
また、沖縄の港湾を東アジアゲートウェイの玄関として発展させ「万国の津梁」を目指すという政策は、私自身のライフワークです。
そのライフワークを推進するために、私とデニーの二人で、月1ベースの勉強会「東アジアの物流拠点としての沖縄の現状と課題」を開催している身でもあります。
したがって、港湾の施策というのは私の活動の中でも大きなウェイトを占めているのですが、今回は港湾議連の主催で、身近でありながら意外と知らない「東京港」の視察に行ってまいりました。
【東京港ホームページ(東京都港湾局)】
http://www.kouwan.metro.tokyo.jp/
さて、私自身も不勉強だったと反省しているのですが、東京港は、今、この瞬間も日進月歩の進化を遂げています。一方で、海も陸も、常に大渋滞。
そんな環境下で、香港・上海・シンガポール・釜山・寧波・ドバイといったアジアの国際港との激烈な競争にさらされているのです。
ここに、「コンテナ取扱量の港湾ランキングの推移(世界)」という参考資料があります。
1991年には178万TEUで世界12位であった東京港。
最新のデータによる取扱量は、約2.4倍の420万TEU。
では、世界ランキングは?
なんと27位に滑り落ちてしまっています。
トップは、上海港の2,907万TEU。
2位は、シンガポール港の2,847万TEU。
3位は、香港港の2,353万TEU。
4位が、深セン港の2,251万TEU。
ここまでが2,000万クラスの取扱量を誇るトップ港です。
すべてが東アジア域に集中しているということも興味深い事実ですが、東京港が取扱量を倍増しているのにもかかわらず、ハブポートとしての存在感を示せなくなっているという事実に、愕然としました。
また、現在、東京・川崎・横浜という近接する三港がそれぞれ経営を異にしていますが、国際競争力の強化のためにも、コスト削減・政策実現のスピードアップという観点からも、三港の一体的な経営が急務といえましょう。
ご参考までに、平成20年のデータになりますが、3港を合算した取扱量は760万TEU。
これはロサンゼルス港の786万TEU に匹敵し、NY港やロングビーチ港を抜いて世界17位までランキングが上昇する値です。
さて、ここからは視察のご報告。議員が上京することの少ない月曜日であるにもかかわらず、20名弱も参加があり、多さに思わず驚きです。
まずは東京ゲートブリッジへ。
中間径間部の橋上に立ちながら東京港を見渡し、しばし説明を受けます。
同行くださった東京都港湾局の担当官によれば、
「世界トップレベル奪還を目指し、日本のハブポートとして北米航路における東アジアの国際ハブポートになる」という将来像を描いているそうです。
そのための重要施策として、「コンテナ物流に関する国際競争力の強化」、
具体的には ①国際基幹航路の維持、②三港の一体的な経営、③港をとりまく交通ネットワークの充実・強化、④船舶大型化への対応、⑤コンテナターミナルの整備・充実、⑥オフドック機能の拡充などを挙げておられました。
東アジアのメインポートとして、大きく変革を遂げて実力を伸ばした韓国・釜山港に対峙できる日本のハブポートを目指すとの力強いご説明に、
「那覇港もうかうかしていられないな」と、
つい地元を思い浮かべてしまいます。
左斜め前方が、羽田空港。羽田側からは海底トンネルでゲートブリッジへ入ります。
しばし、議連でお借りしたミニバスの車窓から東京湾を視察しながら、議員同士で意見交換。選挙区に港湾を抱える議員は、皆さん真剣そのもの。
しかし、バス内で説明があったとおり、ターミナルまでの渋滞に早速巻き込まれてしまいました。東京港は、特に利用者ニーズが高く、ヤード内では常にコンテナで満載状態、周辺道路の青海地区・大井地区の最大渋滞は7Kmにおよび午後4時ごろには通常10分程度の距離で行くべきものが80分もかかってしまう状態になるとのこと。航路の渋滞とともに、大問題です。企業は、こうした物流コストの無駄をもっとも嫌いますので、大商業地・大集積地に近いという東京港のインセンティブが効かなくなってしまいます。
現在、臨港道路南北線事業・臨港道路南北線接続事業が計画されており、これが実現すると現在の混雑箇所のバイパスにもなりますので、輸送力の強化が期待できます。
昼過ぎに、大井埠頭のコンテナターミナルに到着。
埠頭からターミナルを遠景とともに拝見。
前方左の箱状のものが、世界初の立体型コンテナ集積所です。
実は、つい先日の16日~18日、デニーと釜山港・釜山新港を視察に行ってきたばかりです。
その報告は、別の機会にしっかりさせていただきますが、
徹底的に合理化された釜山新港のコンテナターミナルの凄さを身にしみて感じてまいりました。
船舶大型化に対応した水深16メートル、奥行き600メートルの大型バース。
また、1バースあたりガントリークレーンを3~4基配備(通常は2基)、
トランスファークレーンはすべてオートメーション化し、
オペレータールームから遠隔操作するなど、徹底した設備投資ぶりには、驚愕の一言でした。
そして、その設備投資は、国籍を問わない民間資本によるもの。
運営も民間企業による経営です。
大井埠頭コンテナターミナルも懸命にメンテナンスや設備投資を行っていますが、圧倒的な質・量を兼ね備える釜山新港とついつい比較し、しばし無言に。
やはり、港湾政策の充実は急務です。
今日の知見は、釜山港・釜山新港の視察とともに地元に持ち帰り、
那覇港の発展のために活かしてまいりたいと考えています。
万国の津梁を目指し、まだまだ頑張ります!
Posted by 沖縄4区・瑞慶覧チョービン at 13:51│Comments(0)
│港湾施策
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。